「洗浄」という習慣の歴史は古く、紀元前3000年頃のメソポタミア文明にまで遡る「石けん」と共に歩んできた。
古代ローマのサポー(Sapo)と呼ばれる丘では、羊を焼いて神様におそなえする風習があり、したたり落ちた羊の脂と木の灰が混ざり合ったものが、偶然にも洗浄効果を持つことが発見された。
これが石けん(Soap)の原型になったと言われている。
国や地域、時代によって製法に違いはあるものの、長い歴史の中で人類の衛生を支えてきたのは「石けん」だったと言えるだろう。
しかし、20世紀に入ると、石けんは突如として洗浄剤の主役から引きずり降ろされることになる。
第一次世界大戦中のドイツでは石けんの主原料である油脂が食料と競合し、不足したため、油脂を使わない洗剤の必要性が高まった。
ここで石油を原料とする「合成界面活性剤」が登場し、その強力な洗浄力と大量生産の容易さから、瞬く間に世界中に普及していったのだ。
従来の石けんでは落としにくかった頑固な油汚れも簡単に除去できるようになり、私たちの生活は飛躍的に便利になった。
その一方で、環境汚染や生態系への影響といった負の側面も露呈したことから合成洗剤は飛躍的な進化をとげ、環境や肌にやさしいものも開発された。
そんな中、石けんでも洗剤でもない、自然界がひっそりと生み出す「バイオサーファクタント」という、第三の洗浄成分に注目した企業があった。
しかし、それは長らく「未来の洗浄成分」として、論文上の存在に過ぎなかった。
石けんや洗剤で充分に満たされていると考える中、あえて工業的に作り出す技術に加え、経済合理性の壁が高く、実用化が困難な新しい洗浄成分の開発は不要だと考えられてきたのだ。
この「常識」を打ち破り、世界に先駆けてバイオサーファクタントの一種である「ソホロ(成分名:ソホロリピッド)」の実用化に成功した企業がある。それがサラヤ株式会社である。
今回は、サラヤを訪問し、洗浄剤の歴史が抱えてきた課題、そして「ソホロ」がどのようにして「未来」から「現実」の洗浄成分となったのか、その開発秘話に迫る。
さらに、洗剤成分という枠を超え、化粧品、そして再生医療へと広がる「ソホロ」の無限の可能性を探る。
サラヤの原点と「第三の選択肢」への探求

サラヤ株式会社は1952年、戦後間もない混乱期に創業した。
いまでこそサラヤと言えば「ヤシノミ洗剤」というイメージを持たれる方も多いかもしれない。
しかしその原点には、戦後流行した感染症の赤痢から誰もが等しく逃れるための手段として、日本初となる薬用石けん液の開発がある。
人々の衛生・健康・環境を守るという使命感から始まったサラヤは、1971年には環境負荷の少ない植物性洗剤の先駆けとなる「ヤシノミ洗剤」を世に送り出した。

これは、当時、一般的であった石油系合成洗剤による環境汚染という社会課題に対し、「環境を汚さない植物由来の洗剤を」という強い意志から生まれたものであった。
常に「環境を意識した洗浄剤の開発」を企業理念のベースに据えるサラヤは、石けんと合成洗剤、それぞれが持つメリット・デメリットを深く認識していた。
そして、これら二者択一では解決できない環境問題や、将来的な資源枯渇のリスクを見据え、「もっとより良い洗浄剤はないものか」と模索する中で、自然界が生み出す洗浄成分「バイオサーファクタント」に注目したのだ。
しかし、当時のバイオサーファクタントは、あくまで論文上でその可能性が語られるに過ぎず、実用化には至らない「未来の洗浄成分」とされていた。
工業実現性や経済合理性の壁が大きく立ちはだかり、多くの企業がその実現は不可能と考える中、世界に先駆けてその実用化に成功したのがサラヤだったのだ。
「ソホロ」とは?
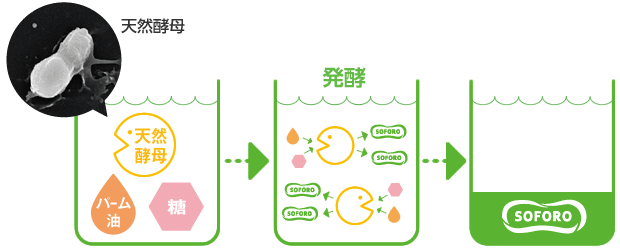
「ソホロ(SOFORO)」は、植物油(主にパーム油)と糖を栄養にして、天然酵母が発酵することによって生み出される天然成分のこと。
合成界面活性剤や石鹸とは異なる「第3の洗浄成分)」と呼ばれており、環境や肌に優しい“未来の洗浄剤”として注目されている。
- 高い生分解性: 排水後、微生物によって速やかに水と二酸化炭素に分解され、地球に還る。
- 高い洗浄力: 環境に優しく安全性が高いにもかかわらず、油汚れから皮脂汚れまでしっかり落とす優れた洗浄力を持つ。
- 低起泡性と優れたすすぎ性: 泡立ちが控えめで、泡切れが良く、すすぎが簡単。
- 高い安全性: 細胞毒性が低く、刺激が少ないため、化粧品や食品成分、さらには再生医療の分野でも利用されるほど安全性が高い成分。
そんな未来の洗浄剤だったはずのバイオサーファクタントを製品化し、現実のものとしてしまったのが、サラヤ総合研究所の平田所長だ。
今回は平田所長から、「ソホロ」の開発秘話についてお話を伺った。
「ソホロ」開発秘話:負の歴史を乗り越える挑戦

———-サラヤでソホロの研究開発をすることになった経緯について教えてください。
平田所長:当社が「ソホロ」の研究を始めたのが1997年ですが、石油系合成界面活性剤が本格的に流通し始めたのは1930年代のことです。
この頃から、化成品としての洗浄剤、例えばボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、台所洗剤、洗濯洗剤など、様々な洗浄剤に界面活性剤が当たり前に使われるようになりました。
それよりも前は、どのように洗浄していたかというと、水で洗ったり、石けんで洗ったりしていました。
ですから、石けんの時代は非常に長く、何千年と続いてきた歴史があります。
そう考えると、石油系の界面活性剤の歴史は、たった100年くらいしか経っていないことになります。
しかし、1930年に始まったにもかかわらず、その消費量はものすごい勢いで増えていきました。
特に高度経済成長期に差し掛かる1970年頃に大きく伸びたんです。日本でいうと、ちょうど和食から洋食へと食生活が変化し、脂っこいものを多く食べるようになった時代です。
そうなると、従来の洗剤ではなかなか汚れが落ちにくくなり、より強力な洗剤が求められるようになりました。
その結果何が起こったかというと、環境に大きな負荷がかかり、川が泡立ったり、富栄養化が進んだりしました。
さらに、環境ホルモン作用を持つ界面活性剤というものがあり、それが川や海に流れ出し、魚がメス化したりするような状況が起こってしまい、使用が禁止された経緯もあります。
急激な使用量の増加と、生分解性の悪さによって環境に蓄積し、水生生物に毒性を与えるという現実が顕在化した結果です。
また、石けんも意外と水の硬度によって洗浄力が影響を受けたり、環境負荷が高いという側面もあります。
石けんは洗剤に比べ、植物油脂の使用量が多く、使用量が増えると水質悪化を招くこともあります。
合成性剤を石けんに置き換えようと思ったら、膨大な量の石けんを生産・消費する必要が出て新たな環境問題が起きてしまいます。
人間の生活の質を下げずに、環境や生物に対しても持続性のある形を考えたとき、合成洗剤と石けんの二者択一では限界があると感じたのです。
こうした背景から、第三の選択肢をつくる必要を感じました。
そして調べていくうちに、生物が界面活性剤をつくる(=バイオサーファクタント)ということが分かり、これを誰も社会実装していないのなら、それに挑戦してみようと決意しました。
———-ソホロを製品化するうえで最も大変だったことは何ですか?
平田所長:洗浄剤としての経済合理性に合致させることです。
たとえば洗濯洗剤は1kgで300~400円で店頭に並んでいますが、バイオでできた製品を量産し、安定供給して店頭に同じ値段で並べられるかといえば、それはさすがに難しいでしょう。
では、多くの人が1回数千円かけて毎日洗濯をするかというと、それもまた現実的ではありませんよね。
しかし逆に、経済合理性が合わないことはほとんどの人が理解しているので、多くの企業はバイオサーファクタントの製品化に積極的に取り組もうとしませんでした。
これが、バイオサーファクタントに関する当時の「常識」だったわけです。
それでも、その常識を突破しようとするところが、いかにもサラヤらしいと感じています。
考えてみれば、ヤシノミ洗剤が誕生したのも、コストの安い石油系合成洗剤の大量生産・大量消費の時代でしたから、その時代にあえてコストが高く、社会的ニーズの低い植物系の洗剤を作るのは勇気がいることだったはずです。
また、今では当たり前となっている家庭用洗剤の詰替えパックもサラヤが日本で初めて発売しましたが、これも当時としては非常に画期的な、そして勇気のいる挑戦でした。
その「勇気」があったからこそ、私たちも第三の界面活性剤という分野にチャレンジできたのだと思います。
———-バイオサーファクタントの商品化に成功した後の反響はいかがでしたか?
平田所長:当社が商品を実用化した後、国際学会で発表したのですが、アメリカの農務省の方から「これは本当か?」と大変驚かれました。
世界中の研究者は、バイオサーファクタントの存在は知っているものの、実用化と経済合理性を両立させることが難しいと理解していますから。
ですから、アメリカ農務省の方は、様々な場所で講演する際に、社会実装例として当社の製品を毎回紹介してくださっていました。
ちなみにいま、世界的にバイオサーファクタントブームが来ていますが、日本が先行している技術でもあるので、海外に後れを取るのは良くないという問題意識を持つメンバーが集まり、勉強会ができました。
参加されている東洋紡さんやカネカさんも、同じ問題意識を共有しています。
———-一番最初にソホロを商品化した際、どんな商品を作られたのですか?
平田所長:ソホロと言えばハッピーエレファントのイメージが強いかもしれませんが、一番最初に実用化されたのは2001年に自動食器洗い機用洗剤として登場した「ソホロン」という商品です。
当時はまだ自動食器洗い機の世帯普及率が5~6%くらいの時代で、専用の洗剤はスーパーやドラッグストアでは買えず、家電専門店にしか置いてありませんでした。
先ほどお話しした「経済合理性」という壁を超えるために目を付けたのが、このニッチな市場でした。
当時、食洗器用の洗剤は「専用洗剤」の種類が限られていたため、キロ単価が非常に高かったのです。
また「泡が立たない」という特殊な性能が求められているのですが、泡が立たない洗浄成分はわずかしかなく、また難生分解性、いわゆる環境に悪い成分しかありません。
そのようなこともあり、洗浄力もあり、環境に優しく、安全性も高い「ソホロン」は差別化が明確になり、少々高くても買ってもらうことができたのです。
それから有難いことに、東芝さんの推奨品にしてもらうことができました。食洗器の「取扱説明書」に、当社の洗剤を掲載してもらったのです。
東芝さんは食洗器メーカーの中でも後発でしたので、同じく食洗器用洗剤としては後発だった当社の洗剤を即決で選んでもらうことができたんです。
———-ソホロンのあとはどのように商品展開していきましたか?
平田所長:「泡が立たない洗剤」というのが非常に特徴的だったので、そのニーズと合致するところに積極的に売り込んでいきました。
たとえばメディカルの領域。血の付いた手術器具をもう一度利用できるよう再処理(リプロセス)する洗浄でも、ソホロを選んでいただいています。
血は固まると取れなくなってしまうので、洗剤を入れた桶の中につけ置きをする必要があります。
手術器具は鋭利な物が多いので、泡が立つ洗剤だと上から見えず、手を切ってしまう危険がありますからね。
他にも、海上自衛隊で食事後の食器を洗う洗浄機用洗剤としても利用していただいています。
公的な機関は、環境に優しいものをいち早く選んでもらえる傾向があるんです。
このように、食器洗い機用、業務用、病院用…といった具合に、当初ソホロは必要に応じて様々な分野で個別に使われていました。
そして、「ソホロが入っている」というコンセプトを前面に出した初めてのブランドとして誕生したのが「ハッピーエレファント」です。
環境問題、原料調達地であるボルネオの生態系、そして人権…これらすべてが良くなるように、という強い想いが込められているのがハッピーエレファントなのです。
洗浄剤を超えた「ソホロ」の無限の可能性
-1024x639.jpeg)
———-ハッピーエレファント以外にはどのように活用されていますか?
平田所長:ソホロは環境に優しいだけでなく、人にも優しい側面があります。
たとえば、赤ちゃん向けのブランド「アラウ.ベビー」にもソホロリピッドが配合されています。
ソホロを入れると、石けん特有のきしみが減ったりする効果があります。
それから、界面活性剤が肌に残留すると、人によってはかゆみを感じることがありますが、ソホロは肌への残留を抑制してきれいに洗い流すことができます。
ハッピーエレファントに使われるようになり、洗浄剤としての可能性を追求していく中で、化粧品の原料としても使われるようになっていきました。
これは、汚れを落とす「リンスオフ」ではなく、化粧品のように肌に残す「リーブオン」、つまり水と油を混ぜて安定化させる乳化技術に応用されたものです。
当社の化粧品ブランド「ラクトフェリンラボ」の中にも、ソホロが使われています。
化学合成の界面活性剤は一切使用せず、ソホロで乳化・ジェル化しているんです。
そして、コスメの場合は界面活性剤を肌に塗るので、細胞毒性試験という安全性試験をしなければなりません。
この試験をやってみると、細胞が死なないことに気が付きました。間違えたのかなと思って何度も試してみたのですが、やはり結果は同じです。
細胞と界面活性剤は相性が悪いので、普通は死んでしまうものなんです。
100倍とか1000倍といった高濃度にしてようやく、少しだけ細胞が死ぬ程度でした。
界面活性作用があるのに細胞毒性が非常に低いことが分かり、これが化粧品に使い始めるきっかけとなりました。
あとはその延長線上で、再生医療という分野にも着手し始めています。
ちょうど同じくらいのタイミングで山中先生がノーベル賞を受賞され、世間でも再生医療が注目されるようになりました。
細胞を患者さんから採取し、iPS細胞にしたり、別の細胞に分化させたりして、もう一度患者さんに戻すのが再生医療ですが、再生医療においては手術を支える周辺ビジネスが非常に重要です。
細胞を採取した後、その細胞を増殖させるビジネスがあったり、増殖させた細胞を凍結保存したり、凍結保存した細胞を輸送したりするビジネスもあります。
そして現在では、細胞を凍結させる際に、細胞内の水分が結晶化して細胞をいためて壊してしまい、細胞が死んでしまうという問題があります。細胞凍結は非常に難しいんです。
しかし、ソホロを使用すると、細胞内の水分の結晶が丸くて小さいため、細胞にダメージを与えることなく凍らせることができます。

そのため、従来から使われている細胞保存液に代わる新しい保存液として商品化を進めており、多くの研究者に使ってもらっています。
ちなみに、私たちは再生医療を扱っている企業が30団体ほど集まる「中之島クロス」という拠点に参画しています。
それぞれの企業が異なる強みを持っており、輸送に強い企業、増殖に強い企業などがある中で、当社は細胞保存液の分野を担っています。
再生医療を当たり前の世の中にするために、多くの企業が集まって連携しているのです。
———-ハッピーエレファント 洗たくパウダーに記載されている「ソホロファインバブル」について教えてください。
平田所長:洗濯機やシャワーヘッドの中に、微細な泡「ウルトラファインバブル」を発生させる機能があるものがありますが、実はハッピーエレファントのパウダーでも同じような泡が発生します。
お風呂に入浴剤を入れると、ブクブクと大きな泡が発生しますよね。泡は集まろうとする性質があるので、小さい泡が一瞬にして大きな泡になり、浮力がついて上に上がっていくんです。
洗剤もパウダー状だと二酸化炭素が発生するので泡が発生するのですが、そこにソホロリピッドが混ざると、泡を包み込んでくれるため、泡が極めて小さくなるんです。
ファインバブルの良いところは、目に見えないくらい小さいので、繊維の微細な隙間にまで入り込んでいくことです。
そのときに界面活性剤ごと入り込んでいくので、通常は届かないところの汚れに界面活性剤を連れて行ってくれるため、通常の洗剤よりも汚れをしっかり落とすことができます。
汚れは繊維の中に蓄積するので、白く見えていても、実は汚れが残っていて、それが空気と触れると酸化して段々黄ばんでいったりします。しかし、ファインバブルがあれば、そういう汚れの蓄積を防ぐことができるんです。
洗濯洗剤のパウダーは、処方をしている人間からすると、お風呂に入れても不思議ではない処方なのですが、実際に、入浴剤としてお風呂に入れている変わった社員がいたんです。
その社員が私に「普通の入浴剤と違うので使ってみてください」と言いうものですから、私も使ってみました。
洗濯パウダーをお風呂に入れた瞬間、浴槽が真っ白になるんです。「あれ?こんなに濁っているものを入れていたっけ?」と思いました。水に溶けるものしか入れていなかったので。
そして10秒くらい経つと、今度は真っ透明になるんです。よくよく観察してみると、真っ白になったのは、濁りではなく「泡」だということに気が付きました。
そして、なぜこんなに泡が小さくなるのか、そしてなぜ浴槽全体が真っ白になるくらい白い泡になるのか、様々な文献を調べてみると、それはファインバブルではないかと。
ファインバブルにも、ウルトラファインバブルであったり、マイクロバブルなどがあります。
マイクロバブルは目に見えるんです。真っ白になっていたのはマイクロバブルだったのです。マイクロバブルができるのなら、それよりももっと微細なウルトラファインバブルも発生しているのではないかということで調べたところ、実際に生成されていることが分かりました。
ほかの界面活性剤で同じ状況をつくっても全くファインバブルができないので、これはソホロ独自の効果であることが分かりました。
ちなみに、ファインバブルの技術は、傷口を洗う洗浄剤にも応用し始めています。
傷口を洗浄すると治りやすくなるんです。褥瘡(床ずれ)や、大きな傷ができて、高齢者や糖尿病の患者さんはとても傷が治りにくいのですが、そのための洗浄剤として使えることが分かってきています。
褥瘡(じょくそう)とは、一般的に「床ずれ」とも呼ばれるもので、同じ姿勢で寝たきりになるなど、体の特定の部分が長時間にわたって圧迫され続けることで、その部分の血流が悪くなり、皮膚や皮下組織、ひどい場合は筋肉や骨までが損傷してしまう状態を指す。
褥瘡回診などは普通に病院で行われています。褥瘡にならないように体位変換をしたりする必要があるのですが、最近は在宅勤務も増えているので、今後は褥瘡が増えるとも言われています。そうした方々のQOL(生活の質)を上げる洗浄剤があったら良いですよね。
それから、介護をされている一般の方でも簡単にできるのが洗浄です。専門家しか使えない難しい器具ではなく、一般の方でもできる方法で傷口を治したり痛みを軽減したりできるのは、非常に意義深いことです。
近く商品化される予定です。ファインバブルにはそんな効果もあるんです。
———-バイオサーファクタントを普及させていくうえでの課題などがあれば教えてください。
平田所長:技術は確立されているのに、法規制が追いついていないところがあると感じています。
特に、製品の裏面表示がボトルネックになっているんです。
というのも、家庭用品品質表示法というものがあるのですが、それは「石けん」か「合成洗剤」かの二者択一の表示しかない状態です。
昭和40~50年代頃の法規制や表現が、そのまま現在も続いている状況なのです。
この二者択一にされてしまうと、ソホロは天然の成分にもかかわらず、「合成洗剤」という表記にされてしまいます。
せっかく環境に配慮した商品を買おうとする賢い消費者が増えているのに、そこが変わらなければ、消費者も選びようがないのが現状です。
バイオサーファクタント勉強会という団体を立ち上げたのも、国に提言したりするため、という側面もあります。
プラスチックにしても、海外では税制法を変えながら、バージンプラスチックよりもリサイクルプラスチックの方が安くなるようにしたりして、積極的に企業の努力を後押ししたりしています。
バイオモノづくりにしても、国が介入し、税制を変えながら、例えば石油系のものを作るよりも、バイオ系のものの方が安くなるようにしたりしてくれれば、消費者としても選びやすくなりますよね。
ハイブリッド車やEV(電気自動車)にも助成金が出ているので、化成品にもぜひ同じような制度を導入して欲しいですね。
消費者がサステナブルな選択肢を選びやすくなるような社会を、皆でつくっていけたらと願っています。
———-今後の展望について教えてください。
平田所長:再生医療で言うと、今はまだ研究の段階なので、それを実際に人に使うとなると、臨床の段階に進まなければなりません。そこのレベルアップはなんとかやり遂げたいですね。
人間の細胞で最も大きな卵子。最近は体外受精の方が増えてきており、今後は妊娠するタイミングも柔軟になってくる可能性があります。
女性の人生の生き方として、妊娠するタイミングをアレンジする時代になってくるかもしれません。
受精卵として凍結保存しておいて、任意のタイミングで妊娠ができる。そうしたところの一助になれる可能性も秘めていると考えています。
それから、発酵のバイオモノづくりからできる洗剤というのは、まだまだ世の中には知れ渡っていないので、洗浄剤としての普及活動も頑張っていきたいです。
海外ではすでに動き始めているので、日本が先行している優位性を維持しながら、負けずに取り組んでいきたいと考えています。
まとめ

古代の日本では、木の灰や植物を利用した「灰汁(あく)」をつかって汚れを落としてきた。
驚くべきことに、古代の人々は、植物の種類によって得られる灰汁の洗浄力が異なることを経験的に知っていたと言われている。
例えば、薪として使われることの多いマツやナラなどの広葉樹の灰は、特に洗浄力が高かったと言われている。
彼らは、まさに自然と共生する中で、その恩恵を最大限に引き出していたのだ。
残念ながら、現代を生きる私たちは、そうした自然との密接な関係から遠ざかってしまい、自然から一方的に搾取し続けている。
しかし、皮肉なことに、今、私たちが直面している環境問題や持続可能性といった課題の解決策は、再び自然界が提供している。それは、最新の科学技術が、太古の人々の知恵と交差する瞬間でもある。
平田所長が語った「ソホロを研究していたつもりが、むしろソホロから”もっと色んな可能性があることに気が付かないのか?”と問われているようだ」という言葉は、この現代における人間と自然の関係を象徴している。
それは、人間が自然を一方的に利用するのではなく、自然の声に耳を傾け、その潜在的な力を共に引き出していくべきだという、深いメッセージを含んでいる。
この言葉は、単に新しい洗浄成分の開発に留まらない。
それは、私たちが自然との新たな関係性を築き、その奥深い可能性に謙虚に学び続けることの重要性を示唆している。
洗浄の未来は、技術の進化だけでなく、我々が自然との共生をいかに再構築していくかにかかっているのだ。











コメント